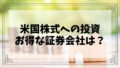株式投資では割安株や成長株といった用語が頻繁に使われます。
非常に有名な概念ですが、何を見て割安株か成長株か判断しているか聞かれることが多いため、一度基本に立ち返ってみようと思います。
この記事では、割安株・成長株とそれを判断するための見るべき指標について紹介します。
割安株・成長株とは何か?
まず割安株・成長株とは何か考えてみましょう。
割安株(undervalued stock / bargain stock)とは、企業が有する価値に比べて株価が割安に放置されていると認められる企業の株式です。その企業が有する価値とは、現在の資産性や収益性からみた企業の価値のことです。
一方、成長株(growth stock)とは、売上や利益の増加が見込まれる企業の株式です。現在の売上や利益が将来には増加、つまり将来の成長性に着眼した銘柄選定を行います。
割安株と成長株の両方に投資する「両刀使い」の投資家は少数派のようで、「割安株派」と「成長株派」に分かれます。私も基本的なスタンスとしては企業の成長性を重視しています。
なお、よく混同されやすい概念として、バリュー・グロースというものがあります。成長株はグロース株と呼ばれることもあります(というか、成長株を英語で言うと"growth stock"です)。しかし、割安株は決してバリュー株と同じではありません。割安株とは、株価が何らかの基準(財務指標など)で見たときに割安な銘柄を意味しており、バリュー株とは、市場価格に織り込まれているリスク・プレミアムが過大であると判断される銘柄のことです。割安株とは例えば同業他社の財務指標と水準を比較して判断されるものですが、バリュー株とは株式評価モデル等で算出されるその企業の本質的な価値と現時点での株価との比較で見るものです。
バリューとグロースについてはこちらの記事でも紹介しています。

割安株・成長株を見るための指標
割安株の場合
割安株を選定するために使う代表的な指標としては、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)、PCFR(株価キャッシュフロー倍率)といった株価を1株あたりの〇〇(利益、純資産、キャッシュフローなど)で割った指標や、配当利回りで判断することが多いです。他には、EV/EBITDA倍率(企業を買収した際に何年で買収資金を回収できるか)という指標が使われることもあります。
これらの指標がある基準、例えば、PERであれば上場企業の場合「15倍」以下、PBRであれば「1倍」以下が割安であると判断されます。
少し考えてみると、この基準は何により決まっているのでしょう?それはほとんどの場合、他社との比較です。PER15倍というのはある時期に調査された日本の上場企業における全業種の平均です。PBR1倍という基準はそもそもその企業の純資産(※資産と負債の差額)と株価により算出される時価総額を比較していることに由来します。実はこのような相対的な判断基準こそが「割安」が割安たる由縁なのです。
例えば、業種Xに属する、ある企業AのPERが13倍だったとしましょう。先ほどの基準通りであれば15倍以下であり、PERの計算にあたり株価が分母ですから、PERの低い場合には株価が低く、割安であることになります。この企業は果たして本当に「割安」なのでしょうか?
さらに、企業Aと同じ業種Xに属し、かなり似たビジネスをしている企業B・企業C・企業Dがあったとします。もし企業B〜DのPERが10〜12倍程度だったらどうでしょう?業種Xにおいて、企業Aはむしろ「割高」である気がしますよね。
つまり、このように割安株を判断するための指標は相対的なもので、比較基準により変わります。
最初の話に戻りますが、割安株と混同される概念である「バリュー株」では、割安株のような判断方法とは異なります。もしある企業Eの株式評価モデルで得られる理論株価が100円にもかかわらず、現在の株価が80円だとします。この場合は、同業他社など置かれた状況に依存せず「バリュー株として優れた銘柄(の候補)」ということになります。
成長株の場合
成長株を探そうとしている投資家は配当金をどれくらいもらえるかを気にしていませんので、配当利回りで銘柄を選定することはありません。また、成長株はPERやPBRで見ると割高になっているケースがほとんどで、これらを用いて銘柄選定することもあまりありません。例えばアメリカのEV大手テスラでは、2020年以降のPERが600倍を軽く超えています。
成長株を探す指標としては、純粋に売上高や利益が伸びているかどうか、ROE(自己資本利益率)が高いかどうかが指標を見る上でのポイントとなります。ROEは「当期純利益」を「自己資本」で割ることにより算出され、ROEが高いということは企業の利益を稼ぐ力が強く、企業内での再投資により企業価値の更なる向上が期待されるため、中長期的な成長性が高いことを示唆しています。
なお、割安株のROEは低いことが多く、PERやPBRで見れば割安であるものの、稼ぐ力や持続的な成長力という面では成長株から劣る傾向にあります。ちなみにROEはPBRをPERで割ることと同義です。
割安株と成長株は二律背反ではない

ここまで割安株と成長株を見てきましたが、実はこれらは二律背反ではなく、割安な成長株というものが存在します。
割安株の指標を紹介したときに説明したように、割安株における「割安」とは相対的な比較ではじめて言えることです。そのため比較対象によっては、成長株の中で割安であるような銘柄が存在することになるのです。
実際、投資手法のひとつにGARP(Growth At Reasonable Price)というものが存在します。GARPでは成長性と割安性の両方を重視しており、バリュエーションを絶対的水準ではなく成長性を考慮して相対的に判断します。つまり、GARPでは中長期の成長性から見て割安な銘柄へ投資します。GARPにおいて参照される指標としては、「PEGレシオ」と呼ばれるPERに成長性を加味した指標があげられ、このPEGレシオをもとに銘柄スクリーニングを行うことが一般的です。
様々な株式へ投資するには?
世界には様々な企業が存在しています。
割安株・成長株に限らず様々な企業の株式へ直接投資するのであれば、証券会社で口座が必要となります。最近では多くの証券会社が海外株式や海外ETFを取り扱うようになってきており、手数料で優劣がかなりはっきりするようになってきました。手数料を比較して実際にどの証券会社を使うか検討してみるとよいでしょう。
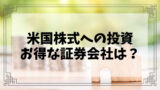
まとめ
ここでは株式投資でよく使われる言葉である割安株や成長株について紹介してみました。その本質は単なる指標や成長性の見込みに左右されるものではなく、常にマーケットでのバリュエーションと照らし合わせて捉えることが必要なのです。
皆さまには株式投資の本質について正しく理解していただき、投資に生かすことで少しでも豊かな生活を送ることのお役に立てればと願っております。